top of page
15年戦争
各項目にカーソルを置くと、サブフォルダーが現れます
日中戦争前史 1874年から1931年
明治に入って日本は周辺国境を確定していった。また満州や清を宗主国とする朝鮮をめぐって清国やロシアさらに米国と摩擦が生じた。すでに多くのアジア諸国を植民地支配においたスペイン・ポルトガル・オランダ・英国・フランスとも大なり小なり対峙する。
1874(明7) 台湾出兵→日清互換条款→琉球日本領
1875 樺太・千島交換条約(樺太→露、千島→日本)
江華島事件→1876日朝修好条規 朝鮮側には「片務的領事裁判権の設定」や
「関税自主権の喪失」といった不平等条約。この後同様の条約を西欧列強と結ぶ。
小笠原諸島領有確認 米英と
1882 壬午事変(大院君らの煽動を受けて、朝鮮の首府漢城(現ソウル)で起こった閔氏政権および日本に対する大規模な朝鮮人兵士の反乱)→済物浦条約(在漢城日本人加虐の実行犯等の逮捕と処罰、日本側被害者の遺族・負傷者への見舞金5万円、損害賠償50万円、公使館護衛としての漢城での軍隊駐留権、兵営設置費・修理費の朝鮮側負担など) 清国軍3,000名、日本軍200名弱の首都漢城(現、ソウル)への駐留
1884 甲申政変(金玉均の急進開化派である独立党によるクーデター。親清派勢力(事大党)の一掃を図り、日本の援助で王宮を占領し新政権を樹立したが、清国軍の介入によって3日で失敗した。日本国内では、公使や日本軍がクーデタに関与した事実は伏せられ、清国軍の襲撃と居留民が惨殺されたことのみが大きく報道されたこともあって、対朝・対清主戦論的な国民世論が醸成されていた。自由党の機関紙『自由新聞』は、「我が日本帝国を代表せる公使館を焚き、残酷にも我が同胞なる居留民を虐殺」した清を許すことはできず、中国全土を武力で「蹂躙」すべしとの論陣を張り、福澤諭吉の『時事新報』も「北京に進軍すべし」と主張した。)
→韓城条約(朝鮮国王の謝罪、日本人死傷者への補償金、日本公使館再建費用の負担などを定めた)
1885 →天津条約(伊藤博文・李鴻章)日清両国は朝鮮半島から完全に撤兵し、以後出兵する時は相互に照会することを義務付け
1891 露シベリア鉄道建設着手 1916全線開通
1894 日清戦争
1894年(明治27年)7月25日~1895年(明治28年)4月17日、日本と清国の間で行われた戦争。
李氏朝鮮の地位確認と朝鮮半島の権益を巡る争いが原因となって引き起こされ、主に朝鮮半島と遼東半島および黄海で両国は交戦。
壬午軍乱以後、閔妃によって清国は李氏朝鮮に対する宗主権を一方的に主張していたため、講和条約の中で日本帝国は、李氏朝鮮に対する清国の一方的な宗主権の放棄承認させた他、清国から台湾、澎湖諸島、遼東半島を割譲され、また巨額の賠償金も獲得した。しかし、講和直後の三国干渉により遼東半島は手放すことになった。戦争に勝利した日本は、アジアの近代国家と認められて国際的地位が向上し、支払われた賠償金の大部分は軍備拡張費用、軍事費となった
1895 下関条約(朝鮮の対清独立、遼東半島・台湾・澎湖諸島割譲)
1896 →三国干渉(独仏露、遼東半島返還)
ロシアは極東進出のために不凍港が必要であり、南下政策を取り満州における権益拡大をはかっていた。ロシアは遼東半島を日本に奪われることで南満州の海への出口を失うことを恐れ、日本の満州進出阻止を目論んだ。ドイツの参加理由は、露仏の接近を妨害すること、ロシアの注意を東に向けて欧州における脅威を減らすこと、ドイツ自身の極東への野心、また皇帝が主張した黄禍論など。
列強は清朝の衰退に乗じて「清国の分割」を進めてきたが、清国内の抵抗を危惧してその動きは緩慢なものであり、戦争による賠償で得たイギリス領香港を例外として、露骨な領有権要求は差し控えてきた。だが、日本の要求はこの列強間の「暗黙の了解」を無意味にするものだった。
列強はこの干渉以降、阿片戦争で香港を得た英国の様に、中国の分割支配に本格的に乗り出すことになった。列強は清に対して対日賠償金への借款供与を申し出て、その見返りに次々と租借地や鉄道敷設権などの権益や、特定範囲を他国に租借・割譲しないなどの条件を獲得していった。
-
ドイツは、1897年に宣教師殺害を理由に山東半島・膠州湾を占領、翌年には租借した。
-
1899年にフランスは広州湾一帯を、イギリスは6月、九龍半島北部 7月、山東半島北側の威海衛を租借した。
-
ロシアも総理大臣の李鴻章へ50万ルーブル、副総理の張蔭桓へ25万ルーブルの賄賂を与え、1896年に秘密協定である李鴻章-ロバノフ協定を結び、1898年、遼東半島南端の旅順・大連の租借に成功する。そして、万里の長城以北と満州に勢力圏を拡大し、極東への野心を現実化していった。
-
イギリスは1898年1月に長江流域からビルマへの鉄道敷設と長江流域を他国に割譲しないことを確認し、さらに香港対岸の新界を租借させた。
-
日本も防衛上最低限の要求として、新規獲得した台湾のすぐ隣にある福建省を他国に租借、割譲することがない旨の約束を取り付けた。
-
朝鮮ではこの干渉の結果、日本の軍事的・政治的権威が失墜する一方、閔妃など親露派が台頭した。
-
これらの動きに対し、清国内で税関業務に関わるイギリス人たちは、租借地を通じた密貿易で清の財政が傾くことを懸念し、アメリカ合衆国に働きかけて門戸開放宣言を発表させる。
-
徳富蘇峰が「自由民権」から「国民的膨張」に「変節」したきっかけとされる。
三国干渉
1895年の日清戦争で清国が日本に敗北して以降、中国大陸をめぐる情勢は一変した。日本への巨額の賠償金を支払うために清国政府はロシア帝国とフランスから借款し、その見返りとして露仏両国に清国内における様々な権益を付与する羽目になったが、これがきっかけとなり、急速に列強諸国による中国分割が進み、阿片戦争以来の清のイギリス一国の半植民地状態が崩壊したのである。
とりわけ、シベリア鉄道の満洲北部敷設権獲得に代表されるロシアの満洲や北中国への進出は激しかった。フランスもフランス領ベトナムから進出して雲南省、広西省、広東省、四川省など南中国を勢力圏に収めていき、北中国を勢力圏とするロシアと連携してイギリスを挟撃してくる恐れが生じた(ロシアとフランスは1893年に露仏同盟を締結しており、三国干渉に代表されるように中国分割においても密接に連携していた)。
これに対抗してイギリス首相ロバート・ガスコイン=セシルは、清国の領土保全を訴えることで露仏が中国大陸におけるイギリスの権益を食い荒らすのを防ごうとした。さらに1896年3月にはドイツ帝国と連携して露仏に先んじて清政府に対日賠償金支払いのための新たな借款を与えることで英独両国の清国内における権益を認めさせた。
また1896年1月にはフランスと協定を締結し、英仏両国ともメコン川上流に軍隊を駐屯させず、四川省と雲南省を門戸開放することを約定した。これによってフランスの北上に一定の歯止めをかけることに成功した。
第二次ボーア戦争(1899-1902)、米比戦争(1899-1913)
1900 立憲政友会
義和団の乱The Boxer Rebellion
「扶清滅洋」(清を助け、西洋を滅ぼす)を叫ぶ宗教的秘密結社義和拳教による排外主義の運動が展開されたが、1900年(光緒26年)に清国の西太后がこの叛乱を支持して6月21日に欧米列国に宣戦布告したため国家間戦争となった。だが、宣戦布告後2か月も経たないうちに、北京の公使館員や居留民保護のため8ヶ国連合軍が北京に進出し、大日本帝国が中でも最大の兵力8000人を投入した。
それまで布教活動は条約港に限り認められていたが、アロー戦争(第二次アヘン戦争)後結ばれた天津条約では、清朝内陸への布教を認める条項(内地布教権)が挿入されており、以後多くの外国人宣教師が内地へと入っていった。この結果、キリスト教は次第に信者を獲得、地域の官僚・郷紳と衝突する。
義和団の乱
ロシアは東三省(満州)一帯を占領した。これが後々日露戦争の導火線の一つとなる。
1901 北京議定書(北京・天津に支那駐屯軍常駐、揚子江に遣外艦隊、膨大な賠償金)
西太后は北京から逃走する途中で義和団を弾圧する上諭を出したが、同時に列強との和議を図るよう李鴻章に指示を出した。「中華の物力を量りて、與国の歓心を結べ」(「清朝の〔そして西太后の〕地位さえ保証されるなら金に糸目はつけるな)1901年9月7日に締結された条約中、もっとも過酷だったのは賠償金の額であった。清朝の歳入が8800万両強であったにもかかわらず、課された賠償金の総額は4億5000万両、利息を含めると9億8000万両に上る。北京周辺の護衛は外国部隊が任務にあたることになった。大日本帝国は北京と天津に清国駐屯軍 (後に支那駐屯軍)を設置した。これはのちの日中戦争初期の主力部隊となる。
1902 日英同盟(清漢における両国の利益を守る)
1月30日にロシア帝国の満州占領など極東進出政策への対抗目的。2年後日露戦争勃発。その後、第二次(1905年:明治38年)、第三次(1911年:明治44年)と継続更新されたが、1921年(大正10年)のワシントン海軍軍縮会議の結果、調印された四カ国条約成立に伴って、1923年(大正12年)8月17日に失効した。
1914年「対華21箇条の要求」などで日本が見せた中国への野心に対する警戒や、日本の中国大陸進出を警戒したアメリカが、日本の勢力を削ぐために、日英同盟の解消を画策した。
支那駐屯軍
日英同盟
孫文 蒋介石
日露協約
南満州鉄道
対華二十一箇条要求
シベリア出兵
石井ランシング協定

1904 日露戦争
1904年(明治37年)2月~1905年(明治38年)9月。南下政策を行うロシア帝国との間で行われた戦争。朝鮮半島と満洲の権益をめぐる争いが原因となって引き起こされ、満洲南部と遼東半島がおもな戦場となったほか、日本海海戦で日本の圧倒的勝利となり、日本はアメリカに斡旋を依頼。ポーツマス条約を締結した。
講和条約の中で日本は、朝鮮半島における権益を認めさせ、ロシア領であった樺太の南半分を割譲させ、またロシアが清国から受領していた大連と旅順の租借権を獲得した。同様に東清鉄道の旅順 - 長春間支線の租借権も得るに至った。しかし交渉の末、賠償金を得るには至らず戦後外務省に対する不満が軍民などから高まった。日本には戦争を継続する余裕はなく、賠償金がなくとも停戦する必要があったが、その背景は国民に知らされなかった。
ロシアでは、ロシア第一革命が起こり、ロシア国内は混乱状態になり、戦争の継続が難しくなった。
日本も国民への増税や、動員兵力が109万人へ達し、死傷者も27万人と国力の消耗が激しかった。
第一次日韓協約 日本人財政、軍事、警務、外交顧問設置
1905 中国同盟会(孫文)
孫文はヨーロッパから帰国をする際にスエズ運河を通った際に、現地の多くのエジプト人が喜びながら「お前は日本人か」と聞かれ、日露戦争での日本の勝利がアラブ人ら有色人種の意識向上になっていくのを目の当たりにした。孫文は生前、日本人とも幅広い交遊関係を持っていた。犬養毅の仲介を経て知り合った宮崎滔天や頭山満・内田良平らとは思想上も交遊し、資金援助を受けてもいた。また、実業家では、松方幸次郎、安川敬一郎や株式相場師の 鈴木久五郎、梅屋庄吉からも資金援助を受けている。宮崎滔天らの援助で東京府池袋にて興中会、光復会、華興会を糾合して中国同盟会を結成。ここで東京に留学中の蔣介石と出会う。
露 血の日曜日
ポーツマス条約(韓国に対して日本が指導権、樺太南半分を 日本へ、旅順、大連租借権、長春以南鉄道権利, 賠償金なし
→日比谷焼き打ち事件)
第二次日韓協約 統監府設置(外交権奪取)
1906
11月26日 南満州鉄道株式会社(長春・旅順)設立
政府は日露戦争の戦費の処理と軍拡財源の捻出に苦しんでおり、巨額の資金を出すことはできなかった。政府は結局、資本金2億円のうち1億円をロシアから引き継いだ鉄道とその附属財源および撫順炭田・煙台炭田などの現物出資とした。残りの1億円は、日清両国の出資とされたが、満鉄設立を不当とする清国は参加せず、民間からの投資は日本での株式募集が2000万円、のこり8000万円は外資による社債で賄うこととした。当時の日本人が満鉄に寄せた期待は大きく、第1回株式募集で1000倍を超える応募。一方、外債募集は、1907年から1908年にかけて3回にわたり、もっぱらイギリス市場に求められた。イギリスで調達したのは600万ポンド(約6000万円)。
政府による事業資金は日本興業銀行から社債などのかたちで投資され、南満洲鉄道への投資は同銀行の対外投資総額の約7割を占めていた。ところが実際には、興業銀行関係対外投資の74パーセントが輸入外資に頼っており、その主たる資金調達先は英米両国であった。その点では英米金融資本への従属が生じており、一見「資本輸入による資本輸出」というべき逆説的な状況。
南満州鉄道は、日本が海外で所有していた最大の企業であり資産であった。満鉄は満州の特産品大豆ー食糧・肥料としての世界商品1の独占的な輸送を中軸として、港湾(大連)、鉱業(撫順・煙台)、製鉄(鞍山)などを兼営する一大コンツェルンであり、総裁・副総裁を政府によって任命され、鉄道付属地の行政権を付与された「満州における国家政策の代行機関」であった。その前身は帝制ロシアが所有・経営していた東清鉄道(のち東支鉄道・中東鉄道)でロシアが清国に承認させた東清鉄道の営業期限は1903年から36年間であったが、日本は1915年21か条要求によって、これを99年間(2002年まで)に延長した。
満鉄が日本の南満州支配の大動脈であったとすれぱ、大連・旅順という不凍港をもつ関東州はいわぱその心臓であった。満鉄と関東州を中心として日本の対満投資額は1930(昭和五)年に16億1700万円にのぼり、列国の対満投資の70%を独占したが、それは日本が国外投資の58%を満州に集中した結果であった。また満州在留日本人は30年末に22万8700人を数えたが、在満邦人は国外における最大の日本人集団であるとともに、中国における最大の外国居留民集団であった。
関東軍の直接の任務は関東州の防備と南満州の鉄道の保護とされていたが、その使命は最大の想定敵国の一つであるソ連との戦争において第一線部隊の任を果すことであった。対ソ戦争において・日本陸軍はバイカル湖以東の要域の占領を目的とし、ハルビン西方に予想される第一会戦に有利な態勢を獲得することを作戦準備の主体としたが、これは南満州の確保と関東軍の存在を前提とする作戦計画であった。また陸軍は満州の資源とくに石炭・鉄を日本の国家総力戦にとって不可欠であるとみなしていた。1907年および08年の「帝国国防方針」では日本の想定敵国の第一にロシアがあげられ、23年の改定でアメリカについでソ連があげられた。
桂・ハリマン覚書(満鉄共同経営)→小村寿太郎破棄
アメリカはポーツマス条約の仲介によって漁夫の利を得、満洲に自らも進出することを企んでおり、日露講和後は満洲でロシアから譲渡された東清鉄道支線を日米合弁で経営する予備協定を桂内閣と成立させていた(桂・ハリマン協定、1905年10月12日)。これはアメリカの鉄道王ハリマンを参画させるというもので、ハリマンの資金面での協力者がクーン・ローブすなわちユダヤ人銀行家で日露戦争で大もうけしたジェイコブ・シフであった。この協定は小村外相の反対によりすぐさま破棄された。日本へ外債や講和で協力したアメリカはその後も「機会均等」を掲げて中国進出を意図したが、思惑とは逆に日英露三国により中国権益から締め出されてしまう結果となった
米国で日本人排斥運動
1907 日露協約(清国の独立、門戸開放、機会均等の実現を掲げた。
秘密協定では日本の南満州、ロシアの北満州での利益範囲を協定した。
また、ロシアの外蒙古、日本の朝鮮(大韓帝国)での特殊権益も互いに認めた。日米確執へ)
第三次日韓協約 韓国軍解散、司法権、警察権奪取
1908 三国協商(英仏露)
1910 韓国併合条約(1918にかけて土地調査事業、土地を奪う。 日本の食料基地化)
大逆事件(検察の捏造、社会主義者 幸徳秋水ら12人処刑)
1911 辛亥革命→清朝滅亡(最後の皇帝、溥儀 満州国執政)
二個師団増設要求→閣議拒否 →陸軍大臣辞職→倒閣
→府中からの首相 →第一次護憲運動(閥族打破・憲政擁護) 犬養毅(立憲国民党)、尾崎行雄(立憲政友会)→大正政変
特別高等警察(特高)設置 思想、言論、社会活動弾圧
1912(大正)1月中華民国成立 孫文米国から帰国し臨時大総統
第三次日英同盟から米国除外
第三次日露協約
(辛亥革命に対応するため、内蒙古の西部をロシアが、東部=後の熱河省を中心
とする地域を日本がそれぞれ利益を分割することを協約、満蒙特殊権益)
1913 第一次国共合作(-27)、孫文国民党、反帝、軍閥打破
10月袁世凱 大総統 北京に中華民国北京政府
孫文、袁世凱に敗れ日本へ亡命
1914 第一次世界大戦
8月23日日本ドイツに宣戦布告 青島占領
ドイツ海軍が無制限潜水艦作戦を再開すると、イギリスをはじめとする連合国から日本に対して、護衛作戦に参加するよう再三の要請が行われた。1917年1月から3月にかけて日本とイギリス、フランス、ロシア政府は、日本がヨーロッパ戦線に参戦することを条件に、山東半島および赤道以北のドイツ領南洋諸島におけるドイツ権益を日本が引き継ぐことを承認する秘密条約を結んだ。
これを受けて大日本帝国海軍は、インド洋に第一特務艦隊を派遣し、イギリスやフランスのアジアやオセアニアにおける植民地からヨーロッパへ向かう輸送船団の護衛を受け持った。1917年2月に、巡洋艦「明石」および樺型駆逐艦計8隻からなる第二特務艦隊をインド洋経由で地中海に派遣した。さらに桃型駆逐艦などを増派し、地中海に派遣された日本海軍艦隊は合計18隻となった。
第二特務艦隊は、派遣した艦艇数こそ他の連合国諸国に比べて少なかったものの、他の国に比べて高い稼働率を見せて、1917年後半から開始したアレクサンドリアからマルセイユへ艦船により兵員を輸送する「大輸送作戦」の護衛任務を成功させ、連合国軍の兵員70万人を輸送するとともに、ドイツ海軍のUボートの攻撃を受けた連合国の艦船から7000人以上を救出した。
その結果、連合国側の西部戦線での劣勢を覆すことに大きく貢献し、連合国側の輸送船が大きな被害を受けていたインド洋と地中海で連合国側商船787隻、計350回の護衛と救助活動を行い、司令官以下27人はイギリス国王ジョージ5世から勲章を受けた。連合国諸国から高い評価を受けた。一方、合計35回のUボートとの戦闘が発生し、多くの犠牲者も出した。
10月3日から14日にかけて、第一、第二南遣支隊に属する「鞍馬」「浅間」「筑波」「薩摩」「矢矧」「香取」によって南洋諸島のうち赤道以北の島々(マリアナ諸島、カロリン諸島、マーシャル諸島)を占領
11月7日に大日本帝国陸軍とイギリス軍の連合軍は、ドイツ東洋艦隊の根拠地だった中華民国山東省の租借地である青島と膠州湾の要塞を攻略した(青島の戦い)
連合国の捕虜となったドイツとオーストリア=ハンガリーの将兵(日独戦ドイツ兵捕虜)と民間人約5,000人は全員日本に送られ、その後徳島県の板東俘虜収容所、千葉県の習志野俘虜収容所、広島県の似島検疫所俘虜収容所など全国12か所の日本国内の俘虜収容所に送られ、終戦後の1920年まで収容された。
特に板東収容所での扱いはきわめて丁寧で、ドイツ兵は地元住民との交流も許され、近隣では「ドイツさん」と呼んで親しまれた。このときにドイツ料理やビールをはじめ、数多くのドイツ文化が日本に伝えられた。ベートーヴェンの「交響曲第9番」(第九)はこのときドイツ軍捕虜によって演奏され、はじめて日本に伝えられた。
1915
袁世凱は共和制を廃止、帝政を復活させ、自らが中華帝国大皇帝に即位する。直ちに反袁・反帝政の第三革命が展開される。翌年、袁世凱は病死するが、段祺瑞が後継者となる。
第一次世界大戦中の1915年1月18日
大隈重信内閣(加藤高明外務大臣)は袁世凱に5号21か条の要求を行った。主に次のような内容であった。
-
第1号 山東省について
-
第2号 南満州及び東部内蒙古について
-
旅順・大連(関東州)の租借期限、満鉄・安奉鉄道の権益期限を99年に延長すること(旅順・大連は1997年まで、満鉄・安奉鉄道は2002年まで)
-
日本人に対し、各種商工業上の建物の建設、耕作に必要な土地の貸借・所有権を与えること
-
日本人が南満州・東部内蒙古において自由に居住・往来したり、各種商工業などの業務に従事することを許すこと
-
日本人に対し、指定する鉱山の採掘権を与えること
-
他国人に鉄道敷設権を与えるとき、鉄道敷設のために他国から資金援助を受けるとき、また諸税を担保として借款を受けるときは日本政府の同意を得ること
-
政治・財政・軍事に関する顧問教官を必要とする場合は日本政府に協議すること
-
吉長鉄道の管理・経営を99年間日本に委任すること
-
-
第3号 漢冶萍公司(かんやひょうこんす:中華民国最大の製鉄会社)について
-
漢冶萍公司を日中合弁化すること。また、中国政府は日本政府の同意なく同公司の権利・財産などを処分しないようにすること。
-
漢冶萍公司に属する諸鉱山付近の鉱山について、同公司の承諾なくして他者に採掘を許可しないこと。また、同公司に直接的・間接的に影響が及ぶおそれのある措置を執る場合は、まず同公司の同意を得ること
-
-
第4号 中国の領土保全について
-
沿岸の港湾・島嶼を外国に譲与・貸与しないこと
-
-
第5号 中国政府の顧問として日本人を雇用すること、その他
-
中国政府に政治顧問、経済顧問、軍事顧問として有力な日本人を雇用すること
-
中国内地の日本の病院・寺院・学校に対して、その土地所有権を認めること
-
これまでは日中間で警察事故が発生することが多く、不快な論争を醸したことも少なくなかったため、必要性のある地方の警察を日中合同とするか、またはその地方の中国警察に多数の日本人を雇用することとし、中国警察機関の刷新確立を図ること
-
一定の数量(中国政府所有の半数)以上の兵器の供給を日本より行い、あるいは中国国内に日中合弁の兵器廠を設立し、日本より技師・材料の供給を仰ぐこと
-
武昌と九江を連絡する鉄道、および南昌・杭州間、南昌・潮州間の鉄道敷設権を日本に与えること
-
福建省における鉄道・鉱山・港湾の設備(造船所を含む)に関して、建設に外国資本を必要とする場合はまず日本に協議すること
-
中国において日本人の布教権を認めること
-
このうち、日本側が重視したのは第二号、なかんずく旅順大連の租借地期限の延長と満鉄及び安奉線の期限の延長であった。
5号条項は秘密・希望条項とされていたがただちにリークされ、報道は中国側が21ヶ条要求を突きつけられたと喧伝し、国際的、主にアメリカからの批判を浴びた。日本は5号条項を後に撤回した。中国国内でも反対運動が起こったが、中国側に日本軍を実力で排除する力は無く、日本側は5月7日に最終通告を行い、同9日に袁政権は要求を受け入れた。袁世凱は自己の地位を強固にするために、日本の横暴を内外に宣伝して中国国民の団結を訴えた。中国国民はこれを非難し、要求を受諾した日(5月9日)を「国恥記念日」と呼んだ。
日本の新聞の多くは、21箇条要求を支持した。石橋湛山率いる「東京経済新報」のみ、反対、批判した。「ドイツが青島をもてば東洋の平和に害があって、日本が青島を持てば東洋の平和に害なしという理由は何か。ドイツが青島を持つだけでなく、日本が南満州をとり、イギリスが威海衛を持ち、フランスが広州湾をもつこと、すべて東洋平和に有害である」 「もっと知りたい日本の現代史」より
アメリカは、満洲における租借地と鉄道の租借期限延長に対しては、特別の反対はなかったが、山東省を満洲と同様な日本の勢力範囲とすることに対しては絶対反対であった。イギリスも、満洲における租借地と鉄道の租借期限の延長には賛成協力したが、長城以南においては最大の競争相手と考える日本を強く警戒し、第5号案を同盟国にも秘密にしたことで不信感を強くし、武昌・九江間の鉄道、南昌・潮州間の鉄道に関する要求に対しては、イギリスの利益を侵害するものとして、3月10日に日本政府に考慮を求めた。
一部は山東条項としてヴェルサイユ条約に反映されたが、1921年ワシントン会議が開催され、第一次大戦で膨張を図った日本への警戒から、日英同盟はグレートブリテン及びアイルランド連合王国にとってロシア帝国とドイツ帝国が消滅したため無用となり、英米関係にも好ましくないために解消。
新たに、米・英・仏・日による太平洋における各国領土の権益を保障し、太平洋諸島の非要塞化などを取り決めた四カ国条約が締結。
米・英・仏・日にイタリア王国を加え、主力艦保有率を米英5、日本3、フランス、イタリア1.67とするワシントン海軍軍縮条約が締結。
全参加国により、中華民国の領土保全、門戸開放、新たな勢力範囲設定を禁止する九カ国条約が締結。
また、石井・ランシング協定が破棄され、日本は山東還付条約で山東省、山東鉄道を中華民国に還付、山東半島や漢口の駐屯兵も自主的に撤兵。
義和団体制ともいわれた列強が中国を共同で分割支配する体制を他国が欧州で戦争している間に犯そうとした、日本の失政。
最終的には1922年の山東懸案解決に関する条約等により、日本軍の撤退と租借地及び公有財産・青島税関の返還が行われ、外国人の青島市政参与権は拒否され、山東省の主要都市も外国人には解放されずに終了した。
3月上海・漢口・広東で日貨排斥運動起こる
青島 日本人 189人(1906年)→24,111人(1922年)
済南 154人(1914) → 5606人(1922)
山東出兵(満州事変への道程)の理由が「日本人居留民保護」
1916 第四次日露協約(第一次世界大戦における日露の関係強化と第三国の中国支配阻止、極東における両国の特殊権益の擁護を相互に再確認した。)
1917 ロシア革命後、11月にソビエト政権が誕生した後、この協約を廃棄したものの、北満州と外蒙古における権益を手放すことがなかった。1921年にソ連軍がモンゴル民族独立を旗印に掲げていたモンゴル人民党を支援し、外蒙古にいた中国北洋政府の駐留軍を追い出したことと、1929年に勃発した中東路事件という二つの出来事はソ連が依然としてこの地域における勢力維持を続けていたと思われるものであった一方、日露戦争の敗北でソ連にとっては、満州地方と内蒙古における日本の権益も触れられてはいけない存在になっていたので、日露戦争後の40年の間にソ連は極東地域における日本との勢力バランス維持に努めていた。満州事変後、日本の支配勢力は満州全域に広がっている状況下で、ソ連として残された利権は東清鉄道の所有権だけであった。その為、
1935年にソ連はその管轄下の東清鉄道を満洲国へ売却したことで満州から撤退したが、外蒙古における権益をそのまま保持していた。
1939年にノモンハン事件の勃発で、ソ連はこれを自分の「縄張り」とする外蒙古が日本から侵食されようとすると見て、日本と四カ月にわたる軍事衝突を行ったが、停戦二年後に調印された日ソ中立条約は日ソ両国間の満州、モンゴル(内蒙古と外蒙古)における双方のそれぞれの権益を再確認し、
1945年2月のヤルタ会談で確認されたモンゴル人民共和国とする国家地位に対する国際認可のきっかけにもなった。
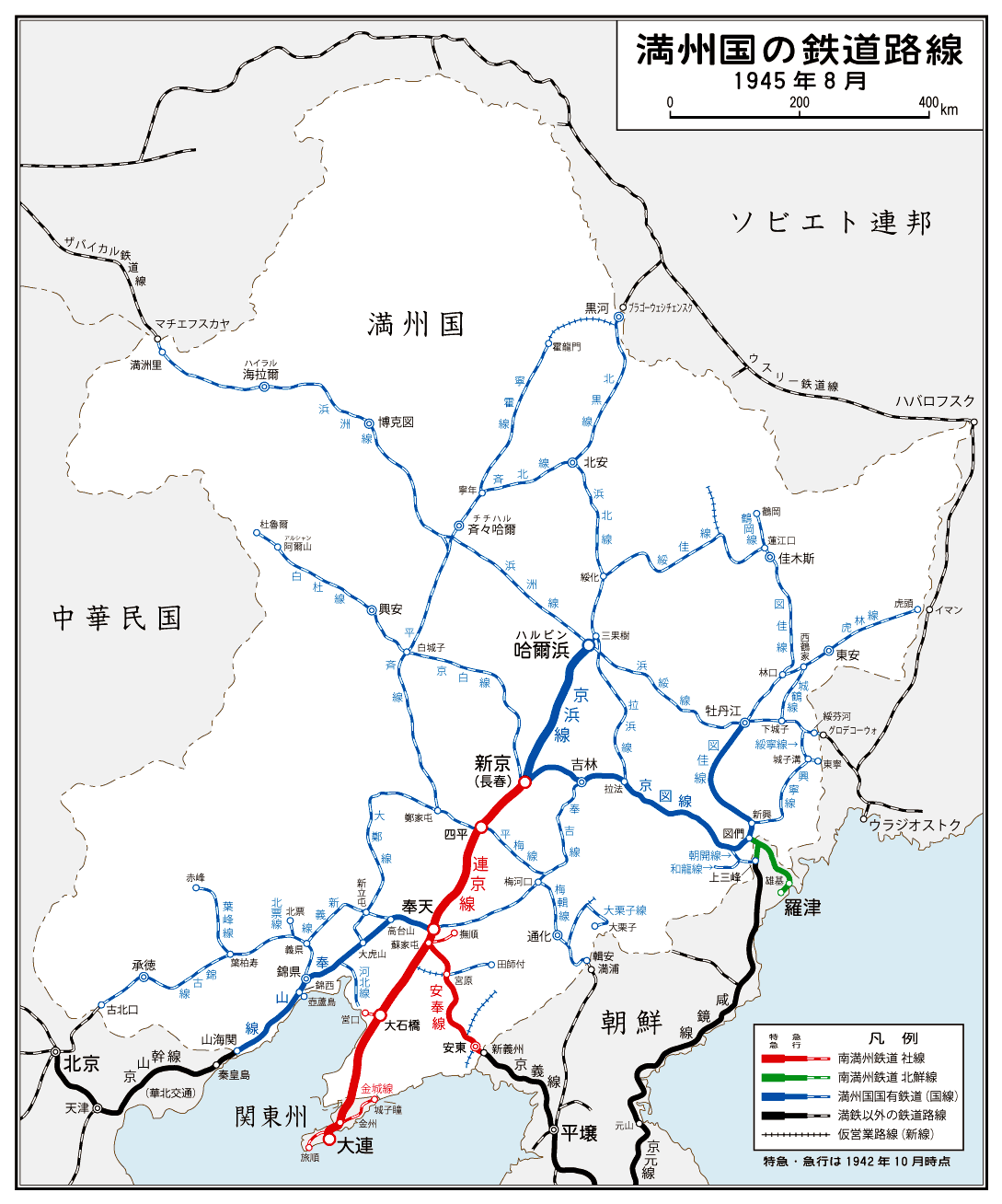

1919(大正8)の三一独立運動以降・吉林省の間島かんとう地方(現在の吉林省東部、延辺朝鮮族自治州一帯)が朝鮮独立運動の根拠地となったことから、南満州にたいする日本の支配は朝鮮統治のためにも強く要請されるようになった。シベリア出兵を継続した理由の一つ。在満朝鮮人は1927年末約80万人を数え、その大部分が間島地方に居住した。
経済的・軍事的・政治的な重要性にもかかわらず、日本の満蒙特殊権益と南満州支配には重大な弱点があった。それはこの権益・支配が中国の主権および民族的利益にたいする侵害のうえに成立していることであった。1919年五四運動以降の反帝国主義ナショナリズムの成長は、中国民族がこのような主権・民族的利益への侵害をもはや許容するものではなくなったことを明示しはじめた。中国の主権回復・民族解放の要求にたいして満蒙特殊権益と南満州支配をいかにすべきかという問題、すなわち満蒙問題は1920年代以降の日本の当面するもっとも深刻な矛盾の一つとなった。そうしたなかで日本がその権益と支配を維持しえた大きな条件の一つは、張作霖という有力な対日協力者が存在したことであった。日本は張作霖を首領とする奉天軍閥を育成し、現地の支柱として利用した。一方、張も日本の援助と庇護を利用して権勢を拡張してきた。しかし張は20年代中頃に中国最大の実力者にのしあがるとともに、日本の統制から離脱しがちとなり、反帝ナショナリズムの高揚のなかで、それにきびしく対決する一方、日本への反発を次第に強めるようになった。
1917年
3月12日ロシアニ月革命、ロマノフ王朝倒れ、臨時政府樹立
4月6日アメリカ、対ドイツ宣戦布告
9月10日孫文を大元帥とする広東軍政府樹立
衰世凱の強権政治に反対して北京を離れ、広東へ政治活動の場を移した孫文や
国民党国会議員ら は、広東軍政府を樹立して北京政府に対抗した
孫文は1919年10月に国民党をより大衆的な政党に改め、広東政府と改称して大総統に選ばれた。孫文は1924年1月に国民党第→回全国代表会議をひらき、ソ連との友好(連ソ)、共産党との合作(容共)、労働者や農民の運動の支援(扶助農工)の三大政策を決定した。これにより国民党と共産党の第一次国共合作が成立し、共産党員も国民党政府・組織・機関に参加して活動できるようになった。
11月7日ロシア10月革命、ソビエト政権樹立
11月 石井ランシング協定
日本の特命全権大使・石井菊次郎とアメリカ合衆国国務長官ロバート・ランシングとの間で締結された、中国での特殊権益に関する協定。
発表された文書では、協定の内容は、日米両国が中国の領土的・行政的統一を尊重して中国大陸における門戸開放政策を支持した上で、日本の中国大陸に於ける特殊権益(於満州・東部内蒙古)を認めるものだった。すなわちアメリカの中国政策の一般原則と日本が主張する特殊利益との間の妥協点を決定するものであった。さらに付属の秘密協定では、両国は第一次世界大戦に乗じて中国で新たな特権を求めることはしないことに合意している。
協定発表時に中国政府(中華民国・北京政府のこと。記事中華民国の歴史を参照)は協定に対する抗議を表明している。
第一次世界大戦のなか、決して激戦地とは言えない東アジア・南洋諸島において参戦した日本が「連合国」として中国大陸に対して権益を拡大しようとすることは英仏米の連合国は快く思わず、その牽制。また、日本は満州権益をその利権を共有してきたロシアとの四次にわたる日露協約による日露の協調を基礎に確保していたが、
1917年欧州内でも農業国のロシアは第一次大戦の工業国による巨額戦費発生に対応できず国民は疲弊、二月革命(ブルジョア革命)及び十月革命(ボリシェヴィキによる帝政ロシア打倒→ロシア内戦~22年→ソ連成立)1918年3月ロシアは第一次大戦から離脱。ドイツは東部戦線が消滅し、西部戦線で英仏などの戦闘に集中。英仏はドイツの目を東に向けさせ同時に革命をけん制するため、日米にシベリア出兵をもちかけた。
日本は満州権益を確保するためにロシアに代わりアメリカとの協調を模索していた。
1918年
3月3日ソビエト、ドイツ・オーストリアと単独講和条約(ブレスト・リトフスク講和条約)調印
5月16日日本、中華民国北京政府と「日中共同防敵軍事協定」締結
7月23日富山県から米騒動発生、たちまち全国へ波及
8月2日日本政府、「シベリア出兵」を宣言
8月3日アメリカ、「シベリア出兵」を宣言、
米・英・仏・伊・日・中の連合国軍によるシベリア干渉戦争開始
11月11日第一次世界大戦終結
シベリア出兵 1922年までの間に、第一次世界大戦の連合国(イギリス・日本・フランス・イタリア・アメリカ・カナダ・中華民国)が「革命軍によって囚われたチェコ軍団を救出する」を名目にシベリアに共同出兵した、ロシア革命に対する干渉。共産主義の封じ込めという目的のほかに帝政時代の外債と、露亜銀行などのさまざまな外資を保全する狙いもあった。
第一次世界大戦中に、ドイツ・オーストリア軍として東部戦線に動員されたチェコ人・スロバキア
人の兵士たちは、ドイツ・オーストリア側にたって戦うことをきらい、各方面から大規模な脱走をおこ
ない、ロシア軍側に投降した。ソビエト政府が戦争を終結させたとき、ロシア領内に五万人のチェコ・
スロバキア軍団が残された。同軍団はソビエト政府の承認をえて、ウラジオストクから船でフランスの
西部戦線に送られることになっていたが、その移動中にシベリア鉄道で反乱をおこしたのである。
日本は8月12日のウラジオストク上陸以来、増兵を繰り返して協定兵力を大きく超える兵力7万3,000人を派兵。
1918年11月に起こったドイツ革命によって第一次世界大戦は停戦する。1919年秋には白軍のアレクサンドル・コルチャーク政権が崩壊したことで英仏による革命政権圧殺の計画は不可能に陥り、ヨーロッパ革命情勢への危惧もあって両国はシベリア撤兵を決定した。アメリカもチェコ軍団の引揚げ完了で出兵目的は達成されたとして1920年1月にシベリア撤退を決定した。これによってシベリア出兵の目的を喪失した連合国各国は、1920年に相次いで撤兵した。しかし日本の原敬内閣は、列国の撤兵後も出兵目的を居留民保護とロシア過激派が朝鮮や満州に影響力を伸ばすことの防止に変更することで駐兵を継続しようとした。そのためアメリカなどから日本への不信感が高まり、日本国内でも批判が高まった結果、1922年10月に日本も撤兵となった。
日本は当初のウラジオストクより先に進軍しないという規約を無視し、ボリシェヴィキが組織した赤軍や労働者、農民によるパルチザンとの戦闘を繰り返しながら、北樺太、沿海州や満州を鉄道沿いにバイカル湖東部まで侵攻し、最終的にバイカル湖西部のイルクーツクにまで占領地を拡大した。
日本は連合国各国よりも数十倍多い兵力を動員し、各国撤退後もシベリア駐留を続けたうえ、さらに占領地に傀儡国家の建設を画策したことから、ロシアのみならず、イギリスやアメリカ、フランス、中華民国などの連合国からも領土的野心を疑われることになった。
この出兵で日本は3500名の死傷者を出し、10億円に上る戦費を消費したうえ、日米関係の悪化を招き、日ソ国交回復の妨げにもなったとされる。
韓国併合条約
辛亥革命

民族自決
朝鮮三・一独立運動
ワシントン海軍軍縮会議
満州放棄論
第一次大戦の話
イギリス海軍の要請により巡洋戦艦「伊吹」がANZAC軍団(Australia/NZ)の欧州派遣を護衛することになった。伊吹はフリーマントルを経てウェリントンに寄港しニュージーランドの兵員輸送船10隻を連れ出発し、オーストラリアでさらに28隻が加わり、英巡洋艦「ミノトーア」、オーストラリア巡洋艦「シドニー」、「メルボルン」と共にアデンに向かった。航海途上で「エムデン」によるココス島砲撃が伝えられた。付近を航行していた艦隊から「シドニー」が分離され「エムデン」を撃沈した。この際、護衛艦隊中で最大の艦であった「伊吹」も「エムデン」追跡を求めたが、結局は武勲を「シドニー」に譲った。このエピソードは「伊吹の武士道的行為」として賞賛されたとする記録がある一方で、伊吹艦長の加藤寛治は、エムデン発見の一報が伊吹にのみ伝えられず、シドニーによって抜け駆けされたと抗議している。以後の太平洋とインド洋における輸送船護衛はほぼ日本海軍が引き受けていた。ところが1917年11月30日に、オーストラリア西岸フリーマントルに入港する「矢矧」に対して、陸上砲台から沿岸砲一発が発射され、矢矧の煙突をかすめて右舷300mの海上に落下する事件が発生した。このような非礼を超えたオーストラリア軍の態度に大日本帝国海軍は激怒し、オーストラリア軍部隊の責任者は、矢矧に乗り込んだ水先案内人が適切な信号を発しなかったため「注意喚起のため」実弾を発射したと弁明したが、結果的に事件はオーストラリア総督とオーストラリア海軍司令官の謝罪により一応は決着した。オーストラリアの日本人への人種差別を基にした、人命にさえ係わる差別的姿勢は戦争を通じて和らぐことがなく、また日英通商航海条約への加入拒否、赤道以北の南洋諸島の日本領有への反対などでも一切妥協しないANZACの態度は、アジア太平洋地域のみならず、第一次世界大戦全体を通じて日本の協力を必須なものと認識しているイギリス本国を手こずらせた。
米騒動(原内閣へ)原敬(政党内閣)
1918年1月8日、アメリカ大統領ウッドロウ・ウィルソン十四か条の平和原則
1917年の十一月革命で成立したロシアのソヴィエト政権が出した「平和に関する布告」(1917年11月18日 / 以下「布告」)に対抗して出された色合いが強いが、それは「民族自決」に関する規定にも現れている。「布告」がヨーロッパ・非ヨーロッパの区別なく植民地を含めた領土・民族の強制的「併合」を否定して民族自決の全面的承認の規定になっているのに対し、同じ連合国で植民地大国であった英・仏などに配慮し、「関係住民(=属領・植民地住民)の利害が、両国の正当な請求と同等の重要性を有する」とかなり限定的な規定になっており、その具体的な適用範囲も、第10〜13条に現れているように、ほとんど敵対する同盟国の領土(ドイツ帝国・オーストリア・ハンガリー帝国・オスマン帝国)に限定され、実質的にはこれらの国の解体を意味する内容であった。しかし、ともかくも帝国主義列強の一角であったアメリカ(およびロシア)が「民族自決」を容認したことの反響は大きく、十四か条における民族自決の適用から外されていたアフリカの大部分やアジアなど植民地・半植民地地域では、この規定を逆手にとって本国(連合国)の政府に対し、より高度の自治や独立を要求する運動が盛んになり、武装蜂起など過激な手段に訴えるなど以後続く民族紛争の切っ掛けともなった。
1919年
1月18日パリ講和会議開催
5月4日パリ講和会議における山東問題の決定に反対する五・四運動
6月28日ベルサイユ条約を調印しパリ講和会議閉幕 中国、条約調印拒否
10月10日孫文、中華革命党を中国国民党と改組・改称、総理に就任
ソビエトは帝政ロシアが中国との間で結んでいた不平等条約の破棄を表明し、中国人の支持と共感を得た。
朝鮮3・1独立運動
1919年3月1日に日本統治時代の朝鮮で発生した大日本帝国からの独立運動。現在の大韓民国(韓国)では肯定的に評価され、3月1日を「三一節(朝: 3·1절)」として政府が国家の祝日に指定。逆に朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)では、失敗したブルジョア蜂起と否定的な評価
アメリカ合衆国大統領ウッドロウ・ウィルソンにより"十四か条の平和原則"が発表された。これを受け、民族自決の意識が高まった李光洙ら留日朝鮮人学生たちが東京府東京市神田区(現:東京都千代田区神田駿河台)のYMCA会館に結集し、「独立宣言書」を採択した(二・八宣言)ことが伏線となったとされる。これに呼応した朝鮮のキリスト教、仏教、天道教の各宗教指導者ら33名が、3月3日に予定された大韓帝国初代皇帝高宗(李太王)の葬儀に合わせ行動計画を定めた。
3月1日午後、京城(現・ソウル)で宣言を朗読し万歳三唱をした。参加者は、しばしば民族代表33人といわれる。運動の担い手はキリスト教、天道教、仏教などの宗教指導者。
吾らはここに、我が朝鮮が独立国であり朝鮮人が自由民である事を宣言する。これを以て世界万邦に告げ人類平等の大義を克明にし、これを以て子孫万代に告げ民族自存の正当な権利を永久に所有せしむるとする。
発端となった民族代表33人は逮捕されたものの、本来独立宣言を読み上げるはずであったパゴダ公園には数千人規模の学生が集まり、その後市内をデモ行進した。道々「独立万歳」と叫ぶデモには、次々に市民が参加し、数万人規模となったという。以降、朝鮮人のキリスト教などの宗教指導者たちのにより、朝鮮半島全体に運動が広がり、5月末までの間に、全国218市・郡の内217の市・郡で200万人以上が参加。海外の朝鮮人も独立運動を起こした。その中にはソウル梨花学堂の16歳の生徒であった柳寛順ユガンスンも含まれる。彼女は忠清南道の故郷に帰り父たちと相談し独立集会を開催、群衆の前で演説。日本軍は発砲し、父母は殺され、彼女は拷問の後、1920年10月12日に獄死した。
朝鮮総督府は、警察・軍隊による武力鎮圧をおこなった。その結果、運動は次第に終息していった。一方司直の手を免れた活動家たちは外国へ亡命し、彼らの国内における独立運動は挫折した。その後の朝鮮半島地域は日本の統治に服し、1945年(昭和20年)の日本敗戦に至るまで大規模な運動は起こらなかった。
発生当時の新聞の論調は「新聞各紙は各地暴動の状況益々悪化しつつありて近く討伐を令せられるべき旨を報じた」とあり、三一運動を暴動とみなしていたが、一部には運動に同情を寄せる識者もいた。たとえば民本主義を標榜し、大正デモクラシーの主導者となった吉野作造は『中央公論』などに朝鮮総督府の失政を糾弾し、朝鮮の人々に政治的自由を与え、同化政策を放棄せよとの主張を発表した。また孫文との交友で知られる宮崎滔天は運動を「見上げたる行動」と評価し、朝鮮の人々の自由と権利を尊重し、いずれは独立を承認すべきと述べている。この他石橋湛山や柳宗悦なども運動への理解を表明している。こうした言論の影響を受け1926年には、総督府とも親密な副島道正による「朝鮮自治論」が唱えられた。対米関係を念頭に置きながら、一貫して朝鮮民族の参政権賦与を唱える副島の主張は政策として採用されることはなかった。
一方、三・一運動で掲げられた要求を受け、総督武官制、軍隊統率権の廃止、地方制度の改正、結社の制限廃止などの法制度改革を一挙に進めていった。憲兵警察制度を廃止し、集会や言論、出版に一定の自由を認めるなど、朝鮮総督府による統治体制が武断的なものから文治的なものへと方針転換される契機となった。朝鮮人による国外での独立運動が活発化する契機となったことや、国内での合法的民族運動を展開する道が開けることになったことは三・一運動の大きな成果といえる。ただそれは日本当局による皇民化政策のより一層の推進を促す結果となったのも事実である。三・一運動後、国内の組織的抵抗が日本側の弾圧によってほとんど不可能になった1922年までの間に、民族主義者にも動揺が現れ「漸進主義」と「急進主義」の分化が見られるようになった。やがて愛国的青年層は「実力の養成」「民族精神の発揮」「団結の必要」などを叫んで「婉曲に排日思想を鼓吹」していたので、総督府側はこの気運を利用し、非難の方向をそらすために「文化運動」が唱えられた。
五・四運動←パリ講和会議から中国抜き(山東省権益日本へ)
パリ講和会議において日本側の「日本がドイツから奪った山東省の権益を容認」という主張が列強により国際的に承認されると、その少し前に朝鮮で起きた三・一独立運動の影響もあって、北京の学生数千人が1919年5月4日、天安門広場からヴェルサイユ条約反対や親日派要人の罷免などを要求してデモ行進をした。袁の後継者である北京の軍閥政権は学生を多数逮捕し、事態の収拾に努めたが、北京の学生はゼネラル・ストライキを敢行、亡国の危機と反帝国主義を訴え、各地の学生もこれに呼応して全国的な抗日・反帝運動に発展した。労働者によるストライキも全国的な広がりを見せ、6月10日には最終的に学生を釈放せざるをえなくなった。また、6月28日に中国政府はヴェルサイユ条約調印を最終的に拒否した。またこの運動は、その広がりの過程において日貨排斥運動へと性質を変え、アメリカ等でも華僑等の誘導による不買運動がみられた。
1920年 尼港(ニコラエフスク)事件
1918年9月アムール川の河口にあるニコラエフスク(尼港、現在のニコラエフスク・ナ・アムーレ)をシベリア出兵に日本軍が占領、1920年1月守備隊がパルチザンに包囲されパルチザンが進駐した。
首謀者はヤーコフ・イヴァノーヴィチ・トリピャーツィンである。
港が冬期に氷結して交通が遮断され孤立した状況のニコラエフスクを、パルチザン部隊4,300名(ロシア人3,000名、朝鮮人1,000名、中国人300名)(参謀本部編『西伯利出兵史』によれば朝鮮人400 - 500名、中国人900名)が占領し、ニコラエフスク住民に対する略奪・処刑、老若男女の別なく数千人の市民を虐殺した。
1921年11月12日
ワシントン海軍軍縮会議
アメリカ、イギリス、日本、フランス、イタリアの戦艦・航空母艦等の保有制限第一次世界大戦が終結した後も、戦勝国となった連合国側は海軍力(特に戦艦)の増強を進めた。軍備拡張に伴う経済負担は各国の国家予算を圧迫。日本を例に取れば、艦隊建造のためだけに国家予算の1/3を使い、維持だけでも半分弱を使うことになる。条約は建造中の艦船を全て廃艦とした上で、米英:日:仏伊の保有艦の総排水量比率を5:3:1.75と定めた。
1921年7月1日 中国共産党結成
社会主義革命を全世界に呼び掛けていたコミンテルンの指示のもと、結成された。しかし、コミンテルンは中国革命の中心的な担い手は共産党ではなく、国民党であり、共産党は国民党を補完するものととらえていたので、中国共産党に対し、国民党との連合戦線を結成するよう求めた。「連ソ・容共・扶助農工」「国共合作」黄埔軍官学校設立(ロシア人顧問派遣、赤軍組織と戦略、教官の中に周恩来、初代校長蒋介石)
(1936年12月蒋介石が張学良に監禁された西安事件の時、共産党から西安には周恩来が派遣され、蒋介石の妻、宋美齢を含んで国共合作が合意されることになる)
1922年
2月4日ワシントン会議において日本と中国、「山東懸案に関する条約」調印
2月6日ワシントン会議において主力艦に関する海軍軍縮条約調印、
「中国の独立・領土保全および関税自主権拡大に関する九力国条約」調印。ワシントン会議閉幕
7月15日日本共産党、非合法に結成される
12月30日ソビエト社会主義共和国連邦(ソ連)成立
ワシントン会議で調印された九カ国条約の発効
中国の独立と行政的、領土的保全を約し、門戸開放と機会均等の原則を承認した。日本の中国進出を抑制するとともに列強による中国権益の保護を図った。日本がドイツから獲得した山東省(膠州湾・青島)のドイツ租借地および山東鉄道(青島-済南間およびその支線)の返還。九カ国には中国に強大な影響力を及ぼし得るソビエト連邦(ソ連)が含まれていなかったのでソ連は中国に接近。
1923年
ソ連は外交官アドルフ・ヨッフェは孫文と共同宣言「中国にとって最も重要で緊急な問題は、中華民国の統一の成功と完全な国家の独立を獲得することにあると考える。ソビエトはこの大事業に対して熱烈な共感をもって援助する」
孫文の妻宋慶鈴は「ロシアは孫博士にとって残された最後の選択だった。100年にわたりあらゆる国々から玄関の靴拭きのように中国は踏まれてきたのです。中華民国ができてからも外国の勢力は中国を植民地のように扱いました。孫博士は各国に何回となく援助を要請しました。だが、いつも侮辱され笑われ、拒否されたのです。ロシアは中国を対等に扱った最初の国なのです。ロシア人は有色人種を劣等なものとして扱わなかったのです」。
1924年(大正13年)には、ソ連は外蒙古を中国から独立させてその支配下におき、また国民党に多大の援助を与えるなど、条約に縛られず自由に活動し得た。アジア・太平洋地域の国際秩序を維持する体制をワシントン体制と言う。日本では、この体制を基盤とする外交姿勢を「協調外交」と呼び、代々、立憲民政党内閣の外相幣原喜重郎らによって遵守された。
1923年9月1日 関東大震災
1923年2月28日、陸軍参謀本部と海軍軍令部は協定して帝国国防方針を改定した。その要点は、
①日本の想定敵国の順位を、露国(ソ連)・米国・支那(中国)と定める。
②ロシア革命後の情勢から対露一国戦争がおこる公算はほとんど想定できず、日本が日清・日露戦争で獲得した満蒙の権益を確保するために、これの回収を望む中国との間に事端が発し、それが発展して、日本対支露との戦争となる場合がもっとも多い。あるいは日本対支米戦争、さらに日本対支露米戦争となることも想定される。
③対露作戦のほか、大陸における所要域(満州・北支・中支の各要域、南支の一局部)の鐡定かんてい(勝利して乱を平定する)に必要な兵力を整備し、その作戦実行上必要な作戦資材の整備を完了する。
これができれば、対支問題から展開して発生する対二国、やむをえない情勢においては、対三国の戦争にも一応堪えうるもくろみをたてえる。
右の帝国国防方針は、日本がシベリア出兵と称したシベリア干渉戦争に敗北して以後に改定したものであるが、すでに中国東北における中国側の日本権益回収を阻止するための満州事変の発動、さらに日中戦争とその延長としての日米戦争さらにはアジア太平洋戦争終盤の対ソ戦も予想して軍備を備えるというものである。歴史はそのとおりに展開することになる。日中戦争全史上
12月30日 ソビエト社会主義共和国連邦(ソ連)成立
1924年1月清浦奎吾(超然内閣・貴族院)
1月20日孫文、国民党第1回全国代表会議開催、
三大政策(連ソ=ソ連との友好・容共=共産党との合作・扶助農工=労働者や農民の運動支援)を決定。これにより国民党と共産党の第一次国共合作(- 27)が成立し、共産党員も国民党政府・組織・機関に参加して活動できるようになった。
第一次国共合作成立
6月16日孫文、黄哺軍官学校設立(校長蒋介石)、国民革命軍(国民党軍)幹部養成
孫文は、辛亥革命において衰世凱に臨時大総統の地位を譲らざるを得なかったのは、革命党が統一された強力な革命軍を持っていなかったためであると認識していた。その教訓から孫文は、ソ連の援助を受けて、二四年六月に広東の黄哺に黄哺軍官学校を設立、蒋介石を校長として、ロシア革命を主導した赤軍をモデルにした国民革命軍(国民党軍)の幹部を養成した。
11月26日モンゴル人民共和国成立
虎の門事件(皇太子狙撃)→山本内閣辞職→6月清浦(貴族院、超然内閣)→第2次護憲運動 反清浦・普通選挙推進 憲政会(加藤高明)政友会(高橋是清)革新倶楽部(犬養毅)政党内閣の時代幣原外交
護憲三派の外務大臣 普通選挙制度(納税要件撤廃、25歳以上男子人口の20.1%女子選挙権なし)
1925年 陸軍軍縮(宇垣陸相)
陸軍でも極東における軍事的脅威が薄らいだことから、帝国議会の追及を受けて山梨半造陸軍大臣のもと二度にわたり軍備の整理・縮小(山梨軍縮)を実施したが、これではまだ不足であるとした政府・国民の不満と、1923年(大正12年)9月に発生した関東大震災の復興費用捻出のため、1925年(大正14年)5月に宇垣一成陸軍大臣の主導の下、第三次軍備整理が行なわれることとなった。将兵約10万人(平時兵力の約3分の1)を削減。
3月12日 孫文死去「革命いまだならず、同志諸君、奮闘努力せよ」
4月22日加藤高明護憲三派内閣により治安維持法公布
5月5日普通選挙法(二五歳以上の男子に選挙権)公布
小日本主義・満州放棄論
小日本主義は、1910年代から1920年代の日本で経済雑誌『東洋経済新報』に拠る三浦銕太郎・石橋湛山らが主張した外交思想。当時の国策の主流であった「大日本主義」を批判するものとして提唱され、政治的・経済的自由主義と結びついていた点に特徴がある。満韓放棄論とも言い、また、より範囲を限定して満州放棄論とも呼ばれる。『東洋経済新報』は、日露戦争後の「三悪法反対運動」(1906年 - 1908年)以降、軍拡財政への反対を主張するようになり、第3代主幹(1907年 - 1912年)の植松考昭のもと、普通選挙の実施と労働者の権利保障を唱道した。植松の急死後、主幹に就任した三浦銕太郎のもとで『新報』は、辛亥革命で動揺する中国への内政非干渉を主張した。また同時期の大正政変では、軍拡路線の元凶である「帝国主義」的国策を否定し、1913年に掲載された論説「大日本主義乎小日本主義乎」では、軍国主義・専制主義・国家主義からなる「大日本主義」に対し産業主義・自由主義・個人主義を3つの柱とする「小日本主義」が提唱された。三浦はまた「満州放棄論」・「移民不要論」を主張し、第一次世界大戦中には日本の青島占領と21ヵ条要求に反対した。日本の植民地統治に関しては、1910年代前半には軍国主義財政批判および保護貿易主義の側面から朝鮮政策を批判し、1910年代半ば以降は植民地を本位とした全面的な政策批判を展開した。三浦による「小日本主義」の主張は1920年代に至って彼を継承して主幹となった石橋湛山のもと、植民地全面放棄論に発展した。1919年、三・一運動に際して湛山が執筆した社説「鮮人暴動に対する理解」は、「鮮人暴動」すなわち三・一運動を世界的規模での新しい民族運動の一環として位置づけ、「凡(およ)そ如何なる民族と雖(いえども)、他民族の属国たることを愉快とする如き事実は古来殆どない」として民族自決を原理的に承認した。また運動の原因を、朝鮮人による「独立自治の要求」に基づくものとの認識を示し、日本の植民地支配それ自体を問題とし、彼らの反抗を緩和する方法は自治付与しかないと結論づけたものである。この主張は「小日本主義」を民族自決主義に基づく植民地政策批判へと一歩前進させるものであった。石橋はさらに、ワシントン会議直前の1921年に社説「一切を捨つるの覚悟 - 太平洋会議に対する我が態度」を発表し、ワシントン会議の主題が「軍備縮小」であるとともに「植民地問題」でもありうるとの認識を示し、同会議において日本が英米に対し優位に立ち会議で主導権を握る政策とは、軍備縮小の提案と「一切を捨つるの覚悟」であると結論づけた。これは朝鮮・台湾などに「自由」を許容し、満州・山東など中国に存在する日本の特殊権益を一切放棄するとの主張を含み、全面的な「植民地放棄論」に到達したものであった。その直後に書かれた社説「大日本主義の幻想」では東アジアにおける「大日本主義」の経済的「無価値」を説き、日本の自立にとって植民地が経済的・軍事的に必要であるとする主張に反論している。また、列強が広大な領土・植民地を有しているのに日本のみがそれを棄てよというのは不公平である、との主張に対しては、たとえば英国のインド支配(イギリス領インド帝国)は、英国にとって「大いなる経済的利益」があると評価し、反面「朝鮮・台湾・樺太ないし満州」は日本にとって経済的利益になっていないと主張した。その上で、日本の発展にとって必要なのは領土よりもむしろ資本であり、経済進出に重点を置くべきであると批判した。その上で、中国・台湾・朝鮮に対し「自由解放」の政策を実施し、より親密な関係を構築するべきと主張した。このように、石橋の小日本主義は植民地支配そのものの否定ではなかったが、植民地放棄を公然と主張したインパクトは小さくないものがあった。
bottom of page